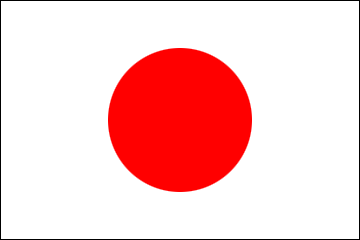概要・申請手続き
令和7年7月31日
草の根・人間の安全保障無償資金協力
序文
日本政府は、開発途上国の多様なニーズに応えるために企画された開発プロジェクトに対して資金援助を行っています。草の根・人間の安全保障無償資金協力として知られるこの制度は、非政府団体(NGO)や地方自治体等の組織が提案するプロジェクトを支援するものです。草の根・人間の安全保障無償資金協力は、草の根レベルの開発プロジェクトに柔軟かつタイムリーな支援を行って大変好評を博しています。
このページでは、草の根・人間の安全保障無償資金協力の目的、草の根・人間の安全保障無償資金協力による資金協力を得るための手続きおよびその他の要件について概説しています。
目的
草の根・人間の安全保障無償資金協力では、NGO、病院、小学校などの非営利団体が開発プロジェクトを実施できるよう支援するための無償資金を供与しています。
各実施対象国における草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金供与は、日本のODAにとって、草の根レベルでの福祉に直接影響を及ぼす新しい協力の手段となっています。
対象団体
どのような種類の非営利団体も、草の根・人間の安全保障無償資金協力の対象となることができます。実施対象国において草の根レベルの開発プロジェクトを実施する非営利団体であるということが唯一の必要条件です。(個人および営利団体は対象となりません。)
支援対象団体の例としては、国際的NGO、現地NGO(国籍は問いませんが、日本NGO支援無償資金協力の対象団体は除きます)、地方自治体、病院、小学校などの非営利団体が挙げられます。特殊な場合には、政府機関や国際機関も援助を受けることがあります。
対象プロジェクトの分野
1)開発プロジェクトが草の根レベルの支援を目指すのであれば、草の根・人間の安全保障無償資金協力による資金供与の対象となりますが、以下の分野が承認プロジェクトの大多数を占めています。
・プライマリー・ヘルス・ケア(基礎的医療)
・初等教育
・貧困緩和
・公共福祉
・環境
対象プロジェクトの例(これに限るものではありません)
・小学校の改修と設備の供与
・病院の改修と医療機器の提供
・井戸の掘削
・障害者の職業訓練
・女性の社会的地位向上のための職業訓練
・中古の消防車、救急車、自転車、机、椅子などの輸送。
(緊急人道支援の場合を除き、古着、文具、食品などの消耗品や個人の持ち物の輸送費は草の根・人間の安全保障無償資金協力の対象となりません。)
・対人地雷除去関連活動、被災者への支援、地雷回避教育
・マイクロ・クレジット(小額短期融資活動)への資金供与
2)優先分野および詳細な条件は、各実施対象国の日本国大使館または総領事館(以下、大使館等という)により、対象国の開発ニーズに応じて決定されます。
利用可能な資金
草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金は、日本政府が毎年プロジェクトごとに申請案件の審査・評価を行った後、被供与団体に供与されます。
プロジェクト1件当たりの供与額は、一般に1,000万円以下(上限は1億円)です。申請予定者は、消耗品(緊急支援または人道的に必要な場合を除く)、施設・設備の運営・維持費、および被供与団体の管理費については資金供与を受けられないことに注意してください。
申請方法
上記の条件を満たし、開発プロジェクト実施のために草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金供与を希望する団体は、自国内の大使館等に申請書を提出してください。申請書には、プロジェクトの詳細な予算、プロジェクト実施地を示す地図、プロジェクトの実施可能性調査、供与資金で購入する物品・サービスの見積り、申請団体の紹介資料(例:パンフレット)や規則書、および申請団体の年間予算書を添付しなければなりません。
申請書およびその他の必要書類は、自国内の大使館等に送付してください。追加情報が必要になる場合もあるため、申請団体の連絡先を必ず明記してください。
申請書の提出に際しては、以下の点に注意してください。
1)資金供与の対象プロジェクト選定に際して、日本政府は、プロジェクトの影響と持続可能性を優先します。まず第一に、申請団体が持続可能な開発プロジェクトを適切に管理できることを大使館等に対して証明しなければなりません。したがって、申請団体の活動実績の詳細な説明があればその手助けになります。
2)上述のように、日本政府は給与などの経常経費については資金を供与することはできません。したがって、プロジェクトに伴って生じる経常経費は、申請団体が独自にまかなえるだけの資金があることを示さなければなりません。
3)金額に見合う価値のあることが確認できるよう、各予算項目ごとに見積額を提出しなけ
ればなりません。
承認手続き
日本政府は、申請されたすべてのプロジェクトを支援することはできません。日本政府による詳細な審査と評価を経たうえで、適切なプロジェクトに対して資金が供与されます。
大使館等は、申請団体から申請書と添付書類を受理した後、以下の措置を取ります。
1)プロジェクトの審査:申請書が受理されると、そのプロジェクトは大使館等の担当官によって審査されます。特にプロジェクトの目的、社会経済的影響およびコストが重視されます。これに基づき、無償資金協力の候補プロジェクトが選定されます。
2)現場視察:大使館等の担当官が候補プロジェクトの現場を視察します。その後、大使館等は資金協力の決定を行います。続いて、この決定は東京の外務本省から承認を得なければなりません。
3)贈与契約:大使館等と被供与団体が贈与契約に署名します。贈与契約には、プロジェクトの件名と目的、被供与団体の名称、各当事者の権利と義務、プロジェクト実施のために供与される上限額、中間報告書と最終報告書の提出日、およびプロジェクトの完了日が明記されます。
4)資金の供与:申請団体が実際に資金を受け取るためには、関連文書を添えて支払請求書を提出しなければなりません。
5)プロジェクトの実施:無償資金は、承認されたプロジェクトの申請書に明記された物品やサービスの購入のためにのみ適切に使用しなければなりません。無償資金が供与されると、合意された予定表にしたがって適時に(原則として1年以内に)プロジェクトの実施を進めることが求められます。
6)当初案の変更:何らかの理由でプロジェクト案を修正する必要が生じた場合、被供与団体は、大使館等と協議し、事前の承認を得なければなりません。(協議および承認は書面によって行う必要があります。)
7)報告書:実施期間中の中間報告書およびプロジェクト終了時の最終報告書が必要となります。(状況により、被供与団体は追加的な中間報告書の提出を求められる場合もあります。)
8)監査:300万円を超える無償資金協力についてはすべて外部監査が必要となります。
その他の要件
1)受け取った資金はプロジェクト実施のためにのみ使用しなければなりません。プロジェクト実施以外の目的に資金が使用された場合、大使館等は、無償資金の返還を請求する権利を留保します。
2)被供与団体は、無償資金の監査を円滑に行えるようにするため、プロジェクト実施の会計を独立して維持することが望ましい。
申請書ダウンロード(ポルトガル語:ワード)
在リオデジャネイロ総領事館経済班メールアドレス:ecopolcgj@ri.mofa.go.jp
日本政府は、開発途上国の多様なニーズに応えるために企画された開発プロジェクトに対して資金援助を行っています。草の根・人間の安全保障無償資金協力として知られるこの制度は、非政府団体(NGO)や地方自治体等の組織が提案するプロジェクトを支援するものです。草の根・人間の安全保障無償資金協力は、草の根レベルの開発プロジェクトに柔軟かつタイムリーな支援を行って大変好評を博しています。
このページでは、草の根・人間の安全保障無償資金協力の目的、草の根・人間の安全保障無償資金協力による資金協力を得るための手続きおよびその他の要件について概説しています。
目的
草の根・人間の安全保障無償資金協力では、NGO、病院、小学校などの非営利団体が開発プロジェクトを実施できるよう支援するための無償資金を供与しています。
各実施対象国における草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金供与は、日本のODAにとって、草の根レベルでの福祉に直接影響を及ぼす新しい協力の手段となっています。
対象団体
どのような種類の非営利団体も、草の根・人間の安全保障無償資金協力の対象となることができます。実施対象国において草の根レベルの開発プロジェクトを実施する非営利団体であるということが唯一の必要条件です。(個人および営利団体は対象となりません。)
支援対象団体の例としては、国際的NGO、現地NGO(国籍は問いませんが、日本NGO支援無償資金協力の対象団体は除きます)、地方自治体、病院、小学校などの非営利団体が挙げられます。特殊な場合には、政府機関や国際機関も援助を受けることがあります。
対象プロジェクトの分野
1)開発プロジェクトが草の根レベルの支援を目指すのであれば、草の根・人間の安全保障無償資金協力による資金供与の対象となりますが、以下の分野が承認プロジェクトの大多数を占めています。
・プライマリー・ヘルス・ケア(基礎的医療)
・初等教育
・貧困緩和
・公共福祉
・環境
対象プロジェクトの例(これに限るものではありません)
・小学校の改修と設備の供与
・病院の改修と医療機器の提供
・井戸の掘削
・障害者の職業訓練
・女性の社会的地位向上のための職業訓練
・中古の消防車、救急車、自転車、机、椅子などの輸送。
(緊急人道支援の場合を除き、古着、文具、食品などの消耗品や個人の持ち物の輸送費は草の根・人間の安全保障無償資金協力の対象となりません。)
・対人地雷除去関連活動、被災者への支援、地雷回避教育
・マイクロ・クレジット(小額短期融資活動)への資金供与
2)優先分野および詳細な条件は、各実施対象国の日本国大使館または総領事館(以下、大使館等という)により、対象国の開発ニーズに応じて決定されます。
利用可能な資金
草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金は、日本政府が毎年プロジェクトごとに申請案件の審査・評価を行った後、被供与団体に供与されます。
プロジェクト1件当たりの供与額は、一般に1,000万円以下(上限は1億円)です。申請予定者は、消耗品(緊急支援または人道的に必要な場合を除く)、施設・設備の運営・維持費、および被供与団体の管理費については資金供与を受けられないことに注意してください。
申請方法
上記の条件を満たし、開発プロジェクト実施のために草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金供与を希望する団体は、自国内の大使館等に申請書を提出してください。申請書には、プロジェクトの詳細な予算、プロジェクト実施地を示す地図、プロジェクトの実施可能性調査、供与資金で購入する物品・サービスの見積り、申請団体の紹介資料(例:パンフレット)や規則書、および申請団体の年間予算書を添付しなければなりません。
申請書およびその他の必要書類は、自国内の大使館等に送付してください。追加情報が必要になる場合もあるため、申請団体の連絡先を必ず明記してください。
申請書の提出に際しては、以下の点に注意してください。
1)資金供与の対象プロジェクト選定に際して、日本政府は、プロジェクトの影響と持続可能性を優先します。まず第一に、申請団体が持続可能な開発プロジェクトを適切に管理できることを大使館等に対して証明しなければなりません。したがって、申請団体の活動実績の詳細な説明があればその手助けになります。
2)上述のように、日本政府は給与などの経常経費については資金を供与することはできません。したがって、プロジェクトに伴って生じる経常経費は、申請団体が独自にまかなえるだけの資金があることを示さなければなりません。
3)金額に見合う価値のあることが確認できるよう、各予算項目ごとに見積額を提出しなけ
ればなりません。
承認手続き
日本政府は、申請されたすべてのプロジェクトを支援することはできません。日本政府による詳細な審査と評価を経たうえで、適切なプロジェクトに対して資金が供与されます。
大使館等は、申請団体から申請書と添付書類を受理した後、以下の措置を取ります。
1)プロジェクトの審査:申請書が受理されると、そのプロジェクトは大使館等の担当官によって審査されます。特にプロジェクトの目的、社会経済的影響およびコストが重視されます。これに基づき、無償資金協力の候補プロジェクトが選定されます。
2)現場視察:大使館等の担当官が候補プロジェクトの現場を視察します。その後、大使館等は資金協力の決定を行います。続いて、この決定は東京の外務本省から承認を得なければなりません。
3)贈与契約:大使館等と被供与団体が贈与契約に署名します。贈与契約には、プロジェクトの件名と目的、被供与団体の名称、各当事者の権利と義務、プロジェクト実施のために供与される上限額、中間報告書と最終報告書の提出日、およびプロジェクトの完了日が明記されます。
4)資金の供与:申請団体が実際に資金を受け取るためには、関連文書を添えて支払請求書を提出しなければなりません。
5)プロジェクトの実施:無償資金は、承認されたプロジェクトの申請書に明記された物品やサービスの購入のためにのみ適切に使用しなければなりません。無償資金が供与されると、合意された予定表にしたがって適時に(原則として1年以内に)プロジェクトの実施を進めることが求められます。
6)当初案の変更:何らかの理由でプロジェクト案を修正する必要が生じた場合、被供与団体は、大使館等と協議し、事前の承認を得なければなりません。(協議および承認は書面によって行う必要があります。)
7)報告書:実施期間中の中間報告書およびプロジェクト終了時の最終報告書が必要となります。(状況により、被供与団体は追加的な中間報告書の提出を求められる場合もあります。)
8)監査:300万円を超える無償資金協力についてはすべて外部監査が必要となります。
その他の要件
1)受け取った資金はプロジェクト実施のためにのみ使用しなければなりません。プロジェクト実施以外の目的に資金が使用された場合、大使館等は、無償資金の返還を請求する権利を留保します。
2)被供与団体は、無償資金の監査を円滑に行えるようにするため、プロジェクト実施の会計を独立して維持することが望ましい。
申請書ダウンロード(ポルトガル語:ワード)
在リオデジャネイロ総領事館経済班メールアドレス:ecopolcgj@ri.mofa.go.jp