供与時にはなかった、スロープ、観客スタンド
-「心身障害者施設(ミナス州イタウナ市)整備」のその後-
サンタモニカ社会福祉法人について
サンタモニカ社会福祉法人は、ミナスジェライス州の州都ベロオリゾンテ市から80kmほど西のイタウナ市にあり、心身障害者に対する治療、リハビリ、社会復帰活動を行っている施設です。当館の草の根・人間の安全保証無償資金協力により、平成21年度に、雨の日や日差しの強い日でもリハビリ運動ができるよう、多目的運動場に屋根を設置しました。また、特に幼少期の子供は聴覚に異常があってもなかなか発見しづらいという事情にかんがみ、早期に聴覚異常が発見できるよう、聴覚測定装置と音響発信装置を購入しました(心身障害者施設(ミナス州イタウナ市)整備)。
平成25年10月10日、そのフォローアップを目的に、再び同施設を訪れました。出迎えてくださったのは、エリアーニ被供与団体会長、ジョルジア副会長、ロジラーニ校長、ヴァレリアコーディネーター、フラヴィア医師(言語療法学)他スタッフ多数と施設の利用者大勢です。
 |
訪問客が絶え間なく訪れる仕組み
まず、聴覚測定装置、音響発信装置の利用状況を見せていただきました。
検査を担当しているのは、フラヴィア医師。毎週火曜の午前・午後、木曜の午前に検査を実施しているのですが、毎回訪れる人は後を絶ちません。週に20~25人、月に100人弱の人々が訪れるわけです。なぜこのような地方の施設に毎回人々が訪れるのでしょうか。
もともとこのあたりに聴覚検査を実施できる施設がなかったからこそ、この団体に機器を供与したのですが、ここまで検査を求める人々が絶え間なく来館するようになったのには理由があります。
出生後の乳児に対し、連邦政府は種々の検査を受けるための健康手帳を交付しています。乳児はこの手帳に記されている項目に従って検査を受けます。イタウナ市にある病院では、これらの多くの検査を実施していますが、聴覚検査については実施していません。そのため病院は、聴覚検査についてはサンタモニカ社会福祉法人に行くよう、来院者に案内をしています。すなわち、出生後の乳児が検査を受けるにあたって、自然とサンタモニカ社会福祉法人を訪れるルートが、本件供与以降に確立されていたのです。我が国が支援した機器の購入によって、サンタモニカ社会福祉法人という一団体のみならず、市全体、さらには周辺市も含め、乳児を含めた検査を求める人々のニーズを満たす体制が確立されていることが見て取れました。
さらに、この施設では、パンフレット、ポスターを作成して聴覚検査を実施していることをPRするとともに、フェイスブックを活用して実施をアナウンスしています。
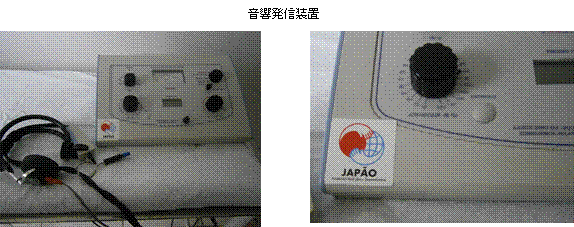 |
||
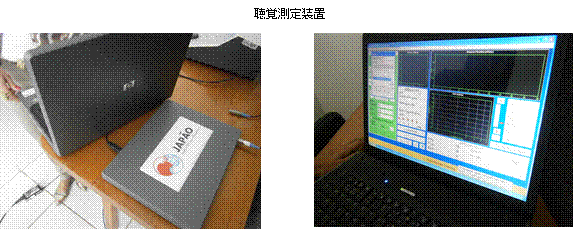 |
||
単純な検査ではない、きめ細やかな対応
特別に、この聴覚検査の現場に立ち会わせていただきました。このとき検査に訪れたのは、生後20日の赤ちゃんとその母親でした。
検査自体は数十秒ほどですが、フラヴィア先生はただ検査をするだけでなく、母親に入念に説明した上で、事前情報を収集します。妊娠中に喫煙や飲酒がなかったか、家族、親族に聴覚異常の人がいないか、などです。事前の問診に使う問診票は独自に作成したものです。
機器のメンテナンスもしっかりしています。年に1回サンパウロの会社に点検に出しているそうです。
さて、検査中、たとえ異常値を来してもすぐに判断はしません。授乳中の雑音や風邪をひいたときの鼻づまりなどによって値は左右されるとのこと。鼻づまりで正確に測れないときは、再度の来館を勧めるそうです。
なお、この赤ちゃんは幸いにも異常が見つかりませんでした。
フラヴィア先生は、4歳になったらまた検査を受けに来るよう、勧めていました。
当分の間は、検査に訪れる人が絶えることはなさそうです。
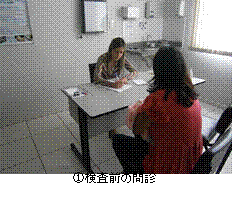 |
 |
|
|---|---|---|
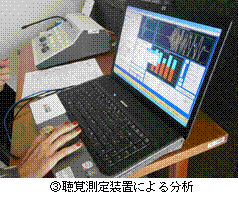 |
 |
|
| ④検査結果は政府発行の健康手帳に書き込まれる
|
「大切に」を、さらに超えて
次に多目的運動場を案内していただきました。
多目的運動場に設置した屋根には、日本の支援を表すマークが堂々と描かれており、利用者にインパクトを与えるとともに、いつも、いつまでも、利用者の心に刻まれることでしょう。
このマークは、屋根を取り付けた当初からあったものなので、施設を訪れる前からその存在は分かっていました。私たちを驚かせたのはこのことではありません。この数年間で、運動場には、スロープや観客スタンドが取り付けられていました。より、使いやすいように、より施設を楽しめるように、自らの手で工夫を重ね改良を施し、より使い勝手のいいものにしてきました。ただ大切に使うのではなく、「大切に」を超えた、“ほんもの”の活用を見た気がしました。
 |
|||
 |
|||
 |
|||
支援がきっかけで、支援を呼ぶ
また、照明器具をつけて夜でも運動ができるようにもしていました。なぜ夜にイベント行う必要があるのかを聞いたところ、「家族が日中働いている場合には、昼のイベントに参加できないため、そのような家族が一緒に楽しめる夜にできるようにした。」とのことでした。6月祭や「オリンピア」と呼んでいる夜の運動会に活用しているそうです。
さらに、隣の空き地には、市の予算でトイレが備わった更衣室を設置する予定だそうです。現在は更衣室がないため、外部団体が利用することはできないのですが、これが完成すれば外部の団体も運動場を利用することができ、この運動場は、サンタモニカ社会福祉法人の施設としてのみ使われるのではなく、地域のコミュニティーの一角を担う存在となるのです。
なお、先に紹介した聴覚検査についても、一部の費用を連邦政府が負担しています。
本件「草の根」支援をきっかけに、利用の幅が増え、また周囲の補助も受け始め、この施設の存在価値や注目度は広がりを見せています。
 |
|||
 |
|||
施設のこれからの展望
本件「草の根」支援とは直接関係ありませんが、最後にサンタモニカ社会福祉法人の施設を少しご紹介いたします。
同施設には、のべ約100人のスタッフと、のべ約400人の利用者がいます。利用者は、赤ちゃんから60代の大人までと、大変幅広いです。
施設では、単に障害者の面倒を見るのではなく、彼らが社会の一員として活躍できるように、自分たちの手でモノを作り、売り出す支援を行っています。例えば、庭にはいくつもの種類の植物が育てられていましたし、施設内では、手作りの紙製品を作っていました。紙製品は、ノートやブックカバー、紙袋などです。この紙製品の原料は、なんと、コンクリート粉が入っていた紙袋(空き袋)で、これを水などで粘土状にし、色をつけたりして加工しているのです。身近にある材料を工夫して、ものづくりに活かしている点においても感服させられます。また、食品作りも行っており、この日見せていただいたのはアイスクリームでした。
同施設では、ますます利用者のニーズが高まっているそうで、市からの予算も来年度は増額が見込まれています。それに伴い、既存の施設や設備では不十分な状況も起こりそうとのことでした。
さらに多くの人々が利用を望む施設になったこの法人に対して当館として支援ができたことをうれしく思うとともに、今後もフォローをして必要な支援をして参りたいと思います。
 |
 |
||||||
 |
|||||||
 |
|||||||